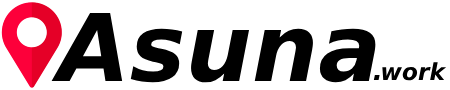母なる川:ラオスのメコン川沿いの旅
東南アジアの背骨に沿って流れるメコン川は、この地域の歴史において極めて重要な役割を果たしてきましたが、特に古代仏教王国ラオスにおいて重要な役割を果たしてきました。
チャンパーサック県を通り、コーヒー農園、隠れた寺院、轟音の滝を通り過ぎてカンボジア国境まで川下りをし、川がラオスの過去、現在、そして未来をどのように形作ってきたかを学びましょう。

パクセから高原へ
川沿いの街に暑く湿気の多い夜明けが訪れる厚いそして、雄大なメコン川での新たな一日が始まる。タグボートやはしけが、石炭、商品、木材を積んだ船を川下へと流していく。ビエンチャン、400マイル北にある。ロングテールフェリーが音を立てて通り過ぎ、通勤者が仕事へ向かい、トラックがタイ国境へ向かう中、街の橋を渡る車が行き交う。水鳥が泥だらけの浅瀬をうろつき、漁師がナマズを捕まえようと網を投げる。
メーナムコン川は「母なる川」と呼ばれています。チベット高原から南シナ海まで2700マイル以上も続くこの壮大な水路は、ラオス絡み合ったチーク色の糸のように。歴史を通じて、王や庶民、兵士や政治家、僧侶や殉教者を運んできた。国境、胸壁、大通りとして機能してきた神聖な水路である。地理的なランドマークであるだけでなく、村や町に水を供給し、乗客や貨物を運び、水田に水をやり、トウモロコシ畑を灌漑する産業動脈でもある。ラオスの生命線である。

「ラオスのこの地域の生活は、ルアンパバーン「私たちは、物事をゆっくり進めるのが好きです。ゆっくり話し、急ぎません。ラオス人民民主共和国の頭文字は、実は「Please Don't Rush(急がないでください)」の略だという古いジョークがあります。個人的には、メコンが私たちの性格を形成したと思います。川のように、私たちは自然のリズムに従います。」
彼は川岸の向こう側を眺める。午前9時過ぎで、東南アジアのほとんどの都市では、この時間にはモペット、タクシー、屋台の喧騒で賑わっているだろう。しかし、川沿いのパクセは、まだ目覚めたばかりのようだ。地元の人たちは歩道のカフェに座ってドラフトをし、時折トゥクトゥクが通り過ぎ、数人の売り子がカートでスイカやパイナップルを売っている。

1 世紀前、パクセの川岸の様子は違っていただろう。この地域の 2 大水路であるセー川とメコン川の合流点に位置するこの都市は、ラオス南部への玄関口であり、その色あせた川岸の建物は、メコン川を見下ろすバルコニーを備えた、植民地時代の大邸宅など、その富の証しとなっている。かつて、この川はラオスのこの地域を通る唯一の交通手段であり、その流れを制御することで権力と繁栄がもたらされた。
メコン川の戦略的重要性は薄れてきたが、ラオスの田舎に住む人々、特にボラベン高原の農民にとって、この川はこれまでと変わらず重要である。メコン川の東30マイルにあるこの肥沃な高原は、火山性の土壌、温暖な気候、そしてメコン川の泥水と栄養分に富んだ水に育まれ、ラオスの野菜の9割とコーヒーのほぼ全量を生産している。
カムソン・スヴァンナキリーさんは、高原に住む小規模コーヒー栽培者の典型です。彼の茅葺き高床式の家は家族の畑を見下ろし、鶏小屋とコーヒーの木に囲まれています。彼はアンティークの鋳鉄製オーブンを使って、注文ごとにコーヒー豆を焙煎します。
「25年間焙煎を続けていると、嗅覚がとてもよくなります!」と彼は言う。「タイマーは使いません。自分の鼻と耳だけです。」彼はひざまずいてハンドルを回し、豆が焙煎できたことを示すパチパチという音を聞きます。5分後、ガスを切って焙煎機のドアを開けます。煙がもくもくと出て、焙煎したてのコーヒーの香りが空気を満たします。「ああ」と彼は微笑みます。「それがボラベンの香りです。」

パクソン村の高原の向こう側では、ナンさんが朝市で農産物を売っている。燻製のカエルの串焼き、メコン川のナマズ、ナス、ズッキーニ、ドラゴンフルーツ、そして高原のもう一つの主要作物であるキャッサバなどだ。「ボラベンはラオスの庭です」と、お客さんのために袋に干しウシガエルを詰めながらナンさんは言う。「ここでは農業は簡単です。土に何か置けば、それが育つのです。それは川のおかげです」

ワット・プーまで川を下る
パクセ港の高原から東に30マイルのところでは、クルーズ船や水上ホテルがメコン川を南下する準備を整えている。物資が積み込まれ、エンジンが始動し、乗客は長旅に備えて客室に腰を落ち着ける。
ゆっくりと、都市郊外は村や水田に取って代わられる。水辺には高床式の家が現れる。牛が川岸を歩き、水牛は浅瀬で涼む。川岸には雨木が立ち、時折、寺院の金色の屋根が霧の中から顔をのぞかせる。それらはメコン川が神聖な川であることを思い出させる。川の浄化と生命の供物としての役割は、ラオスの仏教信仰の中心的柱であり、ジャングルに覆われた川岸には古代の寺院が立ち並んでいる。その中には、最も古く神聖な寺院も含まれる。ワット・プー。
パクセの南25マイルの森林に覆われた山に広がるこの古代寺院は、1000年前に同じヒンドゥー文化によって建てられました。アンコールワット国境を越えたカンボジアには、クメール人が住んでいます。この地に最初に建てられた寺院は 11 世紀から 13 世紀にかけて、シヴァ神を祀ったものです。かつてはここからアンコール ワットまで道路が通っていました。クメール文化が衰退した後、この寺院は仏教徒によって再び占拠されましたが、その後廃墟となり、ジャングルに飲み込まれてしまいました。1914 年にフランスの地質学者アンリ パルマンティエが偶然この寺院を発見するまで、そのまま残っていました。

岩だらけの丘の端に建ち、節くれだったプルメリアの木々が並ぶ急な石段を上った先にあるこの寺院は、インディ・ジョーンズの失われたセットのようだ。寺院の墨のように黒い壁にはヒンドゥー教の神々の彫刻が踊っているが、その半分はつる植物に覆われている。倒れた柱は下草の中に横たわり、苔や地衣類に覆われている。そして内部では、仏教徒が立てた金色の像が薄明かりの中で輝いている。金色の仏像はパラソルに守られ、マリーゴールドと蓮の花の海に囲まれている。再発見されて以来、この寺院は重要な巡礼地となっており、特に満月の時には僧侶たちがメコン川の岸から寺院まで祈りを捧げるために歩いてくる。たまに携帯電話や自撮り棒を使うことを除けば、これは10世紀もの間ほとんど変わっていない信仰の形である。
山の下では、保護活動家たちが建物群の下の建物を修復している。朝の空気にはハンマーとノミの音が響き、女性たちが巡礼者たちに装身具やお供え物を売り込んでいる。その中には、参拝者が寺院に置いていくためのお香の花束を花で包んでいるテム夫人もいる。「お供え物は丁寧に作ることが大切です。慌てないで」と彼女は言い、ピンで留める前に指で茎を切っていた。「もちろん、すべてが完璧であってほしいのですが、それは不可能です。いずれにしても、もう一度挑戦する勇気が湧いてきます。これは人生の良い教訓だと思います」と彼女は付け加えた。

テムさんと彼女の仲間の職人たちは、寺院の近くにあるムアン・チャンパーサックの古い港からやって来た。1世紀前、ここはメコン川で最も重要な港の一つだったが、今では対岸に沿って走るラオスの主要南北道路である国道13号線の開通により、ほとんどの旅行者が通らない忘れられた僻地となっている。
しかし、川の交通はほとんど消えてしまったが、メコン川の昔の生活は別の意味で残っている。川は地元の農民が水田に灌漑するための水を提供しており、それがなければ作物は暑さで枯れてしまう。モンスーンの時期にはメコン川はしばしば堤防を決壊し、平野とその水田は数フィートの水に浸かる。
「川は愛人のようなものだ」と米農家のカイ・ケタヴォンさんは畑で休憩しながら言う。「たいていは優しくしてくれるが、時には教訓を与えたがる。それが人生の真実であり、自然の一部だ。私たちは千年も川のそばで暮らしてきたし、これからも千年は暮らしていくだろう。」
彼は仕事に戻る。午後が夕方に変わり、太陽が山々の向こうに沈み、川の水が桃色に染まる。近くの寺院から夕方の祈りの声が聞こえてくる。ケタヴォンさんは夕食のために、田んぼの間の堤防に沿ってとぼとぼと歩きながら家へ向かう。

島々へ
メコン川がカンボジアに向かって南に流れ、最も幅の広い地点に達すると、川の流れも変化します。1つの川ではなく、複数の川になります。ラオスの南国境から北に約20マイルのところで、メコン川は小川と支流の網に分かれ、地元の言葉で「メコン」と呼ばれる小さな川の島々の群島を形成します。シーファンドン– フォーサウザンド・アイランド。ほとんどの水路は航行するには浅すぎたり狭すぎたりするため、メコン川のこの区間を航行できる船はロングテールフェリーと漁船のみで、エンジンの音を立てながら水路の迷路を進んでいきます。
今ではシーパンドン周辺で大型船を見かけることは稀だが、19世紀後半は違った。フランス植民地時代には、メコン川をインドシナ半島全体を結ぶ交易路に変える計画が立てられ、東南アジアに対するフランスの支配が強固なものとなり、さらには船の建造者に莫大な富がもたらされた。
残念ながら、そこには障害がありました。コネ部門東南アジア最大の滝。幅はナイアガラの滝の4倍、平均水量はビクトリアの滝の10倍。コーンパペンは、幅6マイル近くにわたってゴツゴツした岩や砕けた岩の上に激しく泡立ち、激しく渦巻く白波の塊です。当然ながら、ボートで通行することは不可能で、メコン川を最終的に制御するというフランスの計画において、一見乗り越えられない障害にもなりました。

技術者たちはひるむことなく、島々を横断する4マイルのポーテージ鉄道を建設することで問題を回避することを決定しました。ドン・デットとドン・コンしかし、1893年に開通したこの鉄道は、商業的に成り立つには複雑で費用がかかりすぎたため、1940年代初頭に廃止された。ドン・コン鉄道の名残は、錆びた機関車と、曲がった線路の切れ端だけである。現在、島々を行き来するのは、自転車に乗ったバックパッカーと、田んぼのそばをうろつく水牛だけである。ここも、昔と同じく、主な交通手段は道路でも鉄道でもなく、川である。

ジョン氏はメコン川の気まぐれな流れを熟知している。パートタイムの漁師でもあり、メコン川に迷い込むこともある珍しいイワシイルカを観察する川の観光ツアーも主催している。10年以上川で生計を立てているが、それでも川を完全に信頼しているわけではない。
「川の流れがどうなるかなんて、わからないよ」と彼は、側道からボートを出し、ロールアップを吹かしながら言う。「流れは常に変化している。特に雨期は水深が深くなり、流れが強くなる。砂州が現れ、岩が隠れる。そうなると、川の流れが逆らっているように感じる。でも、この時期は川は穏やかで静かだ」
彼はボートのエンジンを切り、川下へと流しながらイルカを待つ。夕方の早い時間で、川は静寂の絵のよう。聞こえるのはボートの船体にぶつかる水の音と、遠くで牛が鳴く音だけ。白鷺が水面をかすめて飛び、レイン ツリーに止まる。オレンジ色の空にその白い羽が映える。水面には渦や渦巻きが現れ、流れに飲み込まれて消えていく。

「パカ!イルカ!」とジョンさんは船首を指差しながら叫ぶ。水しぶきが上がり、波紋が広がり、淡いピンク色がちらりと見え、尾っぽがちらりと見えたが、すぐにイルカは消えた。「私たちはラッキーでした」とジョンさんは言う。「これは、私たちが今日ここにいることを川が喜んでいる証拠だと思います。」
彼は船をゆっくりと弧を描いて回しながら、ドン・コンへと戻ります。彼の後ろでは、船の航跡がメコン川に広がります。ホタルが水面に輝き、川は焦げたオレンジ色の空を映し返します。流れは変わり、季節は変わりますが、メコン川の岸辺に住む人々にとって、母なる川は流れ続けます。
この記事は2017年9月号に掲載されました。ロンリープラネットトラベラー誌オリバー・ベリーは、選択的アジアLonely Planet の寄稿者は、好意的な報道と引き換えに無料サービスを受け取っていません。
最終更新日は2017年11月です。
サブスクリプション
サイトの新着記事を購読し、新着投稿の通知をメールで受け取るには、メールアドレスを入力してください。