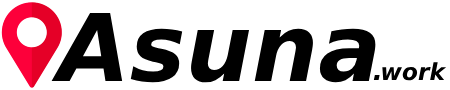太平洋岸北西部の夕暮れの観光
町は静かでした。側面にトワイライトツアーの広告を書いたカーリーな女の子っぽい文字のツアーバスがガソリンスタンドの駐車場に停まっていました。私たちはオリンピック半島自然、深い緑の森、丸太が並ぶ灰金色の砂浜。でもコーヒーにはミルクが必要で、それを手に入れるにはフォークスの吸血鬼と対峙しなければならなかった。キルユート族保護区の傷んだ標識で右折し、北へ向かった。
ステファニー・メイヤーが夜の生き物やエモなティーンたちをこの町に登場させるずっと前から、私はこの陰鬱な伐採の町を訪れていなかった。前回訪れたとき、悪役は絶滅危惧種のアカフクロウだった。「伐採業者を助け、アカフクロウを撃て」や「このビジネスは木材収入で支えられている」は「チーム・ジェイコブ!」に取って代わられた。木こりのチェック柄は、銀色の満月を背景に、エアブラシで不機嫌そうなベラとエドワードの顔を描いた擬似ゴス風のTシャツに取って代わられた。
「ようこそ、トワイライターズ!」と州間高速道路沿いのモーテルの外の看板に書かれていた。道路脇の小さなカートには「トワイライトの薪」の広告が書かれていた。私は、薪が恋に悩む不機嫌な高校生と結びつく商品になったのはなぜだろう、と声に出して不思議に思った。
私たちは雪が溶けたところに車を停め、メインストリートを1ブロックか2ブロックほど歩いて、トワイライトをテーマにしたお店のドアを開けました。そこは広い空間で、すべてが黒と赤と銀色でした。エドワード、ベラ、ジェイコブの等身大の切り抜きが店内のあちこちにランダムに隠れていました。トワイライトのコーヒーカップ、トワイライトのスウェットシャツ、トワイライトのショットグラス、そして特別版のトワイライトの本が入ったベルベットの箱がありました。
店主は奥にいて、驚くほど青白く、ほとんど透明で、肌は青みがかっていた。黒い服を着ていて、防風フリースのジャケットのフードは、ケープの高いスタンドカラーを思わせる複雑な折り紙で折られていた。髪も青白く、黄色がかったブロンドではなく、滑らかで年齢を感じさせない顔に溶け込む中間色だった。そして、私たちに挨拶する彼の声は、甘く高くて柔らかく、ほんの少し訛りのある女性の声だった。
私は店の奥の隅にあるゲストブックをめくった。青いボールペンのハートの中に「チーム エドワード!」「ジェイコブ、愛してるよ!」「ベラとエドワード」と書いてある。目の前の壁には、世界中から来た訪問者がピンで留めた地図が飾ってある。
「そこにいますか?」と店主が尋ねた。「どこから来たのですか?」
「ああ、ここに着いたわ」私はそう言って、夫の故郷を探した。「二人とも。とにかく、十分近いわ。」
「ドイツ語版はここにありますよ…」 身長6フィートはゆうに超えるその男は立ち上がり、全4巻のボックスセットを指差した。彼は夫のアクセント(オーストリア訛り)を察知し、自分のアクセント(南アフリカ訛り)も把握していた。
「2作目は最後まで観られなかった」と私は告白した。「風景が見たくて映画を観たのに、これ以上のことはないわ。」
「妻は本が大好きで、週末に全部読み終えたのですが、私はまだ読んでいません。」
私の頭は完全に停止した。私は店内を見回し、ステファニー・メイヤーのシリーズを次から次へと眺めた。「まだ読んでないの?」と私は繰り返した。
「忙しすぎるんだと思うよ」と彼は言った。
店は空っぽだった。いや、町全体が空っぽに見えた。窓のあちこちに、ふくれっ面の段ボール製のベラやエドワーズやジェイコブが並んでいるのを除けば。
外は雪が激しく降っていたが、チェーンは持っていなかった。ガンメタル色の空は時刻を偽り、まだ午後2時だった。「ここから出ないと」と夫は言った。「フォークスで夜を過ごすつもりはない。」
私たちは車を戻したカラロックビーチ崖の上の小屋が待っていました。夕日と海の匂い。雑貨店を1マイルほど過ぎると、空が開け、背の高い木々には新雪が積もっていました。危険で凍っているように見えた道も、乾いて雪は晴れていました。さらに1マイル進むと、明るい太陽の光に目が眩んでいました。
パム・マンデルはフリーランスのライターです。彼女の作品はウェブ上でご覧いただけます。ワールドハム、ガドリング、実用的な旅行用品、などなど、彼女と会うにはここが一番ですオタクの視点。
吸血鬼や狼男以外の理由で太平洋岸北西部に行くつもりですか?ロンリープラネットのワシントン、オレゴン、太平洋岸北西部旅行ガイド。
サブスクリプション
サイトの新着記事を購読し、新着投稿の通知をメールで受け取るには、メールアドレスを入力してください。