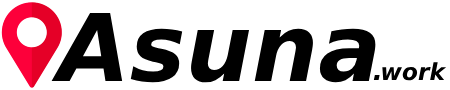ザンベジ川が来てザンベジ川が去る:南アフリカの神話の川沿いの旅
1958 年にブミ丘陵の頂上に立って双眼鏡で外を覗いた訪問者は、上半身裸でつばの垂れ下がった帽子をかぶった男が象を木製のいかだに縛り付けようとしている光景に気を取られたかもしれない。ルパート・フォザーギルは、当時ローデシアと呼ばれた地域、現在のジンバブエ北部の主任狩猟監視官で、新たにできたカリバ湖の水位上昇で取り残された野生動物を移動させる任務を負っていた。

当時の粗い映像には、彼が数々の異常な窮地に立ち向かう様子が映っている。肩まで水に浸かり、うごめくウサギのようなハイラックスを腕に抱えている様子、帽子を一、二度振ってサイを追い払おうとする様子、みすぼらしいヒヒの肩をつかんでボートに引き上げる様子など。1964年に「ノア作戦」が終了するまでに、フォザーギルと彼のチームは6000匹以上の動物を救出した。
現在、ブミの見晴らしの良い場所から見ると、カリバは湖というより海のように見える。岸辺では、象、バッファロー、カバの小さな群れが宝石のように輝く草をはんでいる。正面には、ザンビアのくしゃくしゃした灰色の丘がかすかに見えるが、左右の水平線には水しかない。波間を東から西へと一定の線を描く毎週のカーフェリーは、旅を終えるのに丸24時間かかる。カリバは造られてから50年以上経ったが、容積で世界最大の人造湖であり続けている。しかし、カリバは一時的な現象で、すぐに消えてしまうだろうと考える人もいる。
この地域に住むトンガ族の神話では、ザンベジ川には川の神ニャミニャミが住んでいる。蛇の体と魚の頭を持つ巨大な竜であるニャミニャミは、困難な時期にトンガ族を支えてくれる。1957年と1958年、ジンバブエは記録に残る最悪の洪水に見舞われ、カリバ湖を作るために建設されていた壁が2度も押し流された。トンガ族はニャミニャミは怒っている、ダムは要らないと言った。湖を蛇行する全長200メートルの怪物の目撃情報は今でも地元紙で報じられており、この地域の地震は、反対側に取り残された妻に近づこうとしてこの怪物がダムに激突したためだとされている。

地元ガイドのスチューデント・ムロイワさんは、こうした話を聞いて育った。フォザーギルさんもよく知っている服装(パリッとアイロンをかけたサファリショーツとシャツ)で、木々の梢の間をボートで進む。水面から不気味な指のように突き出ている黒くなった枝は、ザンベジ川がダムで堰き止められたときに失われた、かつてカリバ渓谷を覆っていたモパネの森の名残だ。鵜が枝に止まり、空中に舞い上がっては突然水面下に潜り込み、ヨーロッパで夏休みを終えたばかりのツバメが枝の上を飛ぶ虫を吸い込んでいる。
学生は、周囲の水位が上昇する中、谷を去った最後の人間にちなんで名付けられた島を指差す。「モラはニャミニャミを信じていたので、ダムは不要だと分かっていました。『水が私の家の玄関まで来るはずがない』とモラは言いました。しかし、水はどんどんと来て、彼の家まで来てしまいました」と学生は説明する。「結局、彼はカヌーに乗り込み、漕いで去っていきました。」

学生の母親ウナリーも、湖ができた時に去った一人であり、トンガ族の新しい家となる予定の移住村まで12マイル内陸まで歩いて行った。彼女は日干しレンガの家の陰に座っている。屋根はブルーグラスで葺かれ、外ではブリキの鉢が太陽の下で乾いている。彼女の家族が手入れしている小さな区画では、トマト、サツマイモ、オクラ、トウモロコシが育っている。
小屋の集落の端には、誰もいない監視塔が立っている。夜になると、孫の一人が登って、襲いかかるライオン、ハイエナ、ゾウを見張る。「私はもう年を取りすぎて湖には行けません」とウナリエは言う。「でも、昔の村での生活は完璧でした。ニャミ・ニャミに会ったことはありませんが、彼が壁を壊したければ、私は大喜びです」
その日が来るまで、ザンベジ川のダム建設に適応しなければならない。カリバ川から100マイル下流で、川は濃厚で緩やかな渦を巻いてインド洋へと旅を続ける。氾濫原の春の森から、オークのような広い木々が白い草木々が茂り、この地域は不思議と見慣れた雰囲気を醸し出している。枝の下でシマウマが鼻を鳴らしていなければ、まるで黄金色の夏の日にリッチモンド公園にいるような気分になれるかもしれない。

クラウド・マゴンドは、ここマナ・プールズ国立公園に移り住む前に、ブミ・ヒルズで野生動物ガイドの訓練を始めた。「I ♥ Jesus」と書かれた野球帽を頭に固定し、カヌーに乗り込み、岸から滑り降りる。ホテイアオイの巣からタゲリが飛び出し、狂ったように激しくさえずって敵意を示す。カバの目と耳が水面に浮かび上がる。クラウドはパドルでカヌーの側面を叩く。「3トンもある動物を驚かせてはいけない」と彼は言う。「もし走ってきたら、追いつけないだろう。残るのは破片だけだ」。カバは立ち上がり、目の前に波が押し寄せる中、狭い水路を力強く通り抜けて私たちのほうへ向かってくる。カバがボートの下に飛び込んでタゲリに加わるために私たちを空高く飛ばしてくれるのを待ちながら、緊張した数秒が過ぎるが、カバはまっすぐ走り抜けていく。 「今はワニのことだけを心配すればいいんだ」と、自分よりもアフリカの野生動物に慣れていない人たちをからかうことを大いに楽しんでいる男の笑顔でクラウドは言う。
マナ プールズで最も有名な住人を探すため、ボートは放棄されました。クラウドは下草の中を這い進み、ソーセージ ツリーから落ちた鮮やかな赤い花を踏み越え、枝に巻き付いた緑の斑点のあるブッシュ スネークを鑑賞するために立ち止まります。インパラは草を食むのをやめて見上げ、驚いて逃げ去ります。
筋肉質の雄エランドは、しばらくその場に立っていたが、その後、高慢に茂みの中へと忍び寄った。「見つけたぞ」とクラウドはしゃがみながら言った。「ほら、ボズウェルがいる」。前方には、カリバ湖と同じくらいの年齢の象が、巨大な頭蓋骨をはるかに超える牙をもった象牙の下に立っている。ファイドヘルビア、優しく揺れる。鼻は頭上の樹冠にぶら下がっている種子鞘に届き、背中を反らせ、空中に持ち上げられる。6秒間、犬が物乞いをするように後ろ足でバランスを取り、枝を引き倒す。

ボズウェルと、この地域にいる彼のような数頭のゾウは、このように立つ世界で唯一のゾウだと考えられており、このような姿勢で立っているのが観察されたのはここ 30 年ほどのことだ。一説によると、ザンベジ川のダム建設で公園の生態系が乱れて以来、ファイドヘルビアの木は衰退しており、その実をめぐる競争が激化しているという。「ボズウェルは賢い」と、このゾウが鼻で赤い実を口にすくい上げながら、クラウドはささやいた。「生き残るためには、誰よりも高いところに手が届くゾウでなければならないと悟ったんだ」
近年、行動が変化したゾウはボズウェルだけではない。ザンベジ川の岸から遠く離れたジンバブエ西部に、ワンゲ国立公園がある。ここの風景は、イギリスの公園と見間違えようがない。乾季の真っ只中、カラハリ砂漠から吹き寄せられた土に根付いたもじゃもじゃのとげのある灌木から小さな植物が芽吹く。困ったときに助けに来る川の神はいないが、ワンゲは見捨てられていない。フォザーギルの魂は生き続けている。「聞こえますか?」と、私たちのジープを停車させながら、見習いガイドのアダム・ジョーンズが尋ねた。静かな空気に、一定の水ポンプの音が響く。「公園の鼓動を聞いているんです。」
ワンゲの最初のボーリング井戸は 1929 年に掘られ、雨が降らないときにこの地域の水たまりに人工的に水を補給していました。公園の動物たちは今や、ポンプの音を水が来ることと結びつけています。凸凹した道を少し走ると、灰色の塊が点在する平原が現れます。彼らは移動中です。平原のあちこちから象がやってきます。鼻を激しく振り回しながら、ほこりっぽい地面を目が回る速足でせわしなく走ります。水たまりでは、象たちは水を飲み、浅瀬で水しぶきを上げ、泥の中で転がり、ワニやヒヒを追いかけ合い、楽しそうにフフフと鳴きます。

水場へと続く道は、何百年、いや何千年もの間、象が使ってきた道だ。藪の中を独特の道が通り、まるでアスファルトの上に敷かれたかのようにはっきりしている。今では人間もその道をたどっており、その多くは、ライフルを肩にかけ、ミラーサングラスを頭の後ろに押し上げた、心強い姿のジュリアン・ブルックスタインの後ろについている。「ここで道に迷ったら」と彼は言う。「象の道をたどってください。必ず水場へつながります」。この道を通るのは私たちだけではない。チーター、ハイエナ、ヤマアラシの新しい足跡が道中で私たちの付き添いとなり、小さなクリップスプリンガーレイヨウが、ほこりっぽい土から顔を出した花崗岩の丘から飛び出す。私たちは、骨の山の中に長い牙が横たわった、老いた雄象の全身骨格を通り過ぎた。 「象が死んだところに象牙が埋もれる」とジュリアンは立ち止まって遺体を調べながら言った。「悲しいことに、今ではそれはロマンチックな考えだ」
ジュリアンはプロのウォーキングガイドとして6年間働いてきたが、その間に生きた象やその他ほとんどの野生動物に何度も遭遇してきた。しかし、身を守るためにライフルを撃ったことはまだない。「遭遇の90%は、あなたがどう行動するかにかかっています」と彼は説明する。「これらの動物は逃げる動物に慣れています。追いかけるようにプログラムされているのです。近づいていくと、後ずさりします。」7トンの筋肉と骨の塊に直面したとき、それは最も本能に反する行動かもしれないが、ジュリアンの主張はすぐに証明される。
地上からでは計り知れないほど大きい、50歳の雄象が私たちの存在に腹を立て、大きな耳をパタパタと動かしながらスピードを上げて突進してきた。ジュリアンは叫び、腕を振り、土埃を巻き上げながら象に向かって歩き続けた。象は数メートルまで近づいたところで立ち止まり、少し不安そうな顔をしたが、ついに尻尾を振り、憤慨したように鼻を鳴らして去っていった。「ライオンは象とは少し違う」と、私たちがジープにまたがりながらジュリアンが言った。「十分に近づいたことを知らせるために象はうなり声をあげるんだ。まるで『そこにいろ、そうすれば私たちは友達のままだ』と言っているみたいにね。」

知っておいてよかったです。なぜなら、ワンゲはライオンがたくさんいる地域だからです。夜になると、ライオンの低く低い鳴き声がテントのキャンバスの壁に響き渡り、キャンプのあちこちにライオンが飾られています。ライオンたちは、日中いつでも近くの水場のそばで休んでいて、キリンが水を飲みに慎重に降りてくるのを無関心に見守ったり、互いに転がり合ったり親に飛びかかったりする子ライオンに目を光らせたり、シロアリ塚の小さな日陰で寝そべったりしています。新しい仲間もいます。最近やってきた若いオスのライオンで、地元のライオンの群れから遠ざかるほど賢いのです。ライオンは身を隠し、トラブルに巻き込まれないようにする場所を見つけ、黄色い目で常に周囲に危険がないか見張っています。「ライオンは自分が他のライオンの縄張りにいることを十分承知しています」とアダムは言います。「他のライオンが一晩中吠えているのが聞こえていたはずです。きっと怖がっているのでしょう。
「若いライオンは勇気を振り絞って留まり、自分の縄張りをめぐって優位なオスと戦うかもしれない。神経質な様子からすると、ゆっくりと茂みを横切り、絶えずどもりがちに音が鳴る水場を通り過ぎ、さらに先へと進み、自分の群れを作れる縄張りを探す可能性の方が高そうだ。ワンゲのライオン1頭は最近、研究者らによって約120マイル離れたビクトリア滝まで追跡された。

ワンゲの滝と似ていない風景を想像するのは難しい。滝は、はるか遠くの茂みの向こうからでもその存在を知らせる。最初はかすかな轟音が聞こえ、遠くの高速道路のラッシュアワーの交通のような音が数マイル離れたところから聞こえる。次に、低い灰色の雲が地平線にうずくまる姿が見えてくる。この滝に付けられた、より適切な現地語の名前であるモシ・オ・トゥニャ(「轟く煙」)の勢いが最大限に発揮されるのは、平原が突然消え去った時だ。ザンベジ川は縁から100メートルの落差で地面に激しくぶつかり、まるで上向きに降ることを決意した雨のように、4分の1マイルも空中に立ち上がる霧を生み出す。滝の周囲を曲がりくねって進む訪問者は、すぐに水しぶきでびしょ濡れになる。 滝のすぐそばの水たまりに座ったり、足にバンジーロープを結んでビクトリア滝橋から飛び降りたりと、自己保存の常識をすべて無視して無謀な行動をとる人々もいる。
地球を裂いた峡谷を覗き込んでも、底の気配はなく、ただ渦巻く雲と、一連の虹が突き刺さっているだけ。もしニャミ・ニャミがカリバ・ダムへの最後の攻撃を企てる隠れ家を選ぶとしたら、それはこの峡谷にとぐろを巻いた場所だろう。いつの日か、彼は立ち上がり、川を取り戻すだろう。突破するのは時間の問題だ。
この記事はロンリープラネットトラベラーマガジンアマンダ・カニングは、&超えてLonely Planet の寄稿者は、好意的な報道と引き換えに無料サービスを受け取っていません。
https://shop.lonelyplanet.com/products/lonely-planets-best-in-travel-paperback-2019
サブスクリプション
サイトの新着記事を購読し、新着投稿の通知をメールで受け取るには、メールアドレスを入力してください。