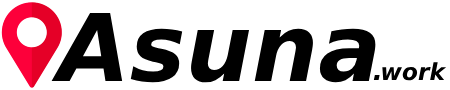「時には、言葉なしで見知らぬ人と最高の会話が生まれる」スコットランド高地での親切な行為
私たちは、素晴らしい旅行記のカタログを探索し、大小さまざまな旅の物語を深く掘り下げています。
フラン・パルンボのこの作品は、スコットランドでの迂回が彼女を再び正しい道へと導いた物語を語っています。見知らぬ人の優しさ。
景色は私の心の中を映し出している。灰色で、霧雨が降り、憂鬱だ。一週間前にここに来てから毎日雨が降っているが、この場所を嫌いになることは難しい。

薄い霧が厳粛な起伏のある地形を覆い、巨大なパステル画のような柔らかく繊細な外観を与えています。日中は太陽が時折顔を出し、アイボリー色の北極光が遠くの丘や崩れかけた石壁を照らし、まるでキャメロットの入り口が目の前にあるかのようです。インヴァネスウィックへ向かう途中、私は赤い小型レンタカーのギアを左ハンドルでシフトした。まるで今までずっと道路の反対側を運転してきたかのように。世界から隠れるには、この場所以上に良い場所はないでしょう。スコットランド高地?
3か月にわたる激動の後にインド、私は思い切って寄り道してみることにしましたスコットランド帰る途中サンフランシスコうだるような暑さ、極度の貧困、完全な混乱、そして閉塞感を覚えるほどの群衆という、あまりにも最近の出来事がまだ頭の中を渦巻いていた。私の胃は、悪意を持って私の腸に寄生した寄生虫のせいでまだむかむかしていた。インドでの彼女のもてなしに対して私が十分に感謝していないと非難した親友との、おそらくは埋めがたい亀裂が、私を孤独にさせた。さらに、私は、インドに出発する前に悲惨な結末を迎えた、辛い失恋にまだ苦しんでいた。アジア私の人生という小さな太陽系内の誰もが私に何かを求めているようでした。私は同胞に対する許容レベルを超えていました。私の全身と魂はガルボ風の「私は一人になりたい!」という声で響き渡りました。
今、ドーノック、ブローラ、ダンビースといった海岸沿いの町を巡りながら、私は計画的に立ち止まって写真を撮ったり、地図に小さな赤い星で記された城跡を訪れたりしています。この斑点模様の赤い星は数十個あり、私はそれぞれの星の象徴となる場所を必ず見に行こうと決心しています。これで私は夢中になり、頭の中でうわ言を吐く悪魔の声を静めることができます。しかし、腹部の声はそう簡単には鎮まりません。グロテスクな悲鳴を上げます。食べないと。
長いドライブの一日だったので、地図上の太字の書体から判断して、このあたりで一番大きな町のように見えるウィックに立ち寄るつもりです。しかし、到着してみると、歴史的な石造りの建物が数軒と、老朽化が進んだような三つ星ホテルが数軒ある以外は、陰気な場所でした。夕方の早い時間で、ボリュームたっぷりの食事と快適な部屋でゆっくりしたいだけなのに、そのまま車で通り抜けました。
北へ進むと、道は人通りが少なくなり、最終的にダンカンスビーヘッドスコットランド本土の最北東端に位置するジョン・オグローツ港村は、その中心にひっそりと佇んでいます。この風に吹かれたスコットランドのこの一角は、何もなく平坦で、陸と空と水だけがあり、強い海風が吹き抜けています。夏にはここからフェリーに乗って、オークニー諸島だが、それ以外は、地図に点として載せる価値もほとんどない。家庭的なレンガ造りの B&B はなく、町の中心地も見当たらない。道路を挟んで向かい側には長方形の 50 年代風モーテルが 2 軒あり、数隻の船が停泊しているだけの水辺から半キロほどのところにある。キャラバン パークが奇妙なことに右手にあり、大型車が何台かランダムに駐車されており、まるで現代の奇妙なモノリスのようだ。さらに悪いことに、レストランは見当たらない。ここは地球上で最も寂しい場所のようだ。

地図を見ると、次の町は遠いようだ。文字が小さすぎる。泊まる場所すらないかもしれない。仕方なくシービュー モーテルにチェックインし、スーツケースを部屋に置いた。小さな窓の 1 つからは人けのない道路が見え、部屋の中央の壁にはピンク、緑、白の模様のシェニール ベッドカバーがかかったゴツゴツしたダブル ベッドが置かれている。ベッドの上には、釣り竿を持った天使の安っぽくて色あせたプリントが掛けられている。ジョン オグローツは、おいしい夕食と一晩の休息のために身を寄せて過ごしたいと思っていた魅力的な場所ではない。
モーテルのフロント係に、まだ夕食を提供しているかもしれない1キロほど離れた場所へ案内され、私は疲れ果てて再び車で出発した。少なくとも数時間は雨が降っていない。暗く重苦しい雲の間から夏の太陽がじっと輝き、ゆっくりと地表に向かって沈んでいく。私は北の端にいるため、夜11時頃まで暗くならないだろう。
以前は小さな教会だったような質素な建物に到着し、中に入ってカウンターに向かい、食べ物を注文した。頭上の黒板メニューには、太いチョークの文字でハンバーガー、サンドイッチ、スープが並んでいる。店内はクエーカー教徒の会議室のように簡素で、揚げ物の匂いと厨房からの音が漂っている。フィッシュアンドチップスを注文し、明日は健康的な食事をしようと心に決め、堅木張りの床に点在する数少ないテーブルの中から、陽気な夫婦のオーナーに案内されて座った。他の客は、黒くてだぶだぶのズボンとウィンドブレーカーを着た、小柄な白髪の男性で、70代くらいに見えるが、隣のテーブルから恥ずかしそうに微笑んでくれた。
「そうだね。」彼は私のほうにうなずいた。私もうなずき返した。
「あなたはこの辺りの出身ではないですよね?」
「いいえ」と告白します。「カリフォルニアから来ました。ただ旅行で来ただけです。」ちくしょう。地元の人たちに溶け込んで誰にも邪魔されないようにしたいと思っていたのに。
「それで、オークニー諸島までフェリーで行くつもりですか?」
「いや、あまり考えてなかったんです。ただ運転してるだけ。あまり見るものはないと思ったんです。」
「まあ、考えてみたらいいよ。去年ここに来て、フェリーに乗って一日過ごしたんだ。素敵だったよ。」
彼は、バードウォッチングや古代遺跡(リング オブ ブロッガーと呼ばれる)について、ガイドブックのような独白を始めた。私は、フェリーのスケジュールやアトラクションへの行き方など、道順や詳細を教えられた。私は行かないとわかっていても、興味があるふりをして、この情報をすべて知りたいかのように会話をする。実際、彼と話したいとも思わない。黙って食事をしたいし、頭の中で起こっていることをすべて聞きたい。この友好的なおしゃべりは私を疲れさせるが、彼はとても親切で感じのいい人なので、とにかく話しかける。彼は一人だ。きっと寂しいのだろう。

フィッシュ アンド チップスの大きな皿が目の前に置かれ、私はサクサクの茶色い塊を口に押し込むのが待ちきれない。数分後、まるで私の食事の邪魔をしたくないかのように、老人はテーブルから立ち上がり、軽くお辞儀をして目を輝かせながら握手を交わし、私と話をして楽しかったと言ってくれた。
夜も更けてきたので、モーテルに戻って水辺まで散歩して夕日を眺めたいと思い、残りの食事を平らげてカウンターへ向かい支払いを済ませた。オーナーは私が差し出した紙幣を払いのけた。
「支払い済みです」と彼は私に言った。私は困惑した。
「あの老人は帰るときに君の分も払ったよ。」
見知らぬ人が私の夕食代を払ってくれて、その親切に何の感謝もせずに立ち去ったことに驚き、私は微笑んで「なんて優しいの」と思った。これまでの旅でこんなことをしてくれた人は誰もいなかったし、私はとても感動した。この数か月間、出会った人全員が生きていて、息をしている「私にくれ」という機械のように感じていたが、世界の片隅で、ただ与えるために与え、見返りは求めず、「ありがとう」さえも求めない一人の人に出会った。皮肉なことに、この小さな行為は、彼が知るよりもずっと大きなものだった。私はその老人を見つけたいという、言い表せない衝動に駆られ、彼に感謝したいという切実な欲求に駆られた。私は彼の名前さえ知らない。
案の定、はるか先の道端に、ポケットに手を入れてよろよろと歩いてくる彼の黒い影が見えた。「乗せてあげましょうか」と、彼の横に車を寄せて尋ねた。彼の顔は満面の笑みで輝き、喜んで申し出を受けた。背は低く機敏で、鼻はぴんと上を向いている。一瞬、レプラコーンに出会ったのかもしれないと思ったが、たとえあり得るとしても、こんなことが起こる国ではないと気付いた。私はモーテルに戻り、車を駐車して、私たちは並んで海辺に向かって歩き、本土とオークニー諸島を隔てるペントランド湾の海岸線まで歩いた。
彼の名前はウォルター。スコットランド国境の下にあるニューキャッスルという街の出身で、キャラバンパークに滞在している。私の心を読んだかのように、彼は何気なく「妻は数年前に亡くなったんだ」と言い、ハイランドの風景そのものと同じくらい物思いにふけり、寂しそうな表情になった。一瞬、私は別のばかげた考えを思いついた。自分が70歳だったら、ウォルターと一緒に彼のトレーラーハウスで残りの人生をスコットランド中を旅できるのに、と。彼は私の腕に触れ、数百メートル離れたところにある何かを指さした。
以前は気づかなかった古いビクトリア朝のホテルが、海岸近くのはるか遠くの影の中に幽霊が出るように佇んでいる。「何年も前から閉まっているんだ」とウォルターは教えてくれた。彼はジョン・オグローツによく出かけており、私が辺りを見回すと、その理由がわかってきた。太陽は、地平線との避けられないキスを長引かせようとしているかのように、空の低いところに垂れ下がっている。波打つ雲の間から、幅広くドラマチックな光の茎が放射され、荒涼とした平原にまっすぐに建つ遠くの家の幻想的な背景となっている。その家は、私が感じているように、寂しく孤独だが、照らされている。一緒にそこに立っている私たちは、ありそうもないペアだが、冷たい古代の海から吹き込む癒しの力に惹かれ、似た者同士である。
魅了されながら、私たちは太陽が徐々に世界の果てに消えていくのを眺めます。最高の会話は、知らない人と言葉なしで生まれることもあります。ここで、ウォルターと一緒に、私は人類への信頼を取り戻すかもしれません。
その他の素晴らしい旅行記:
サブスクリプション
サイトの新着記事を購読し、新着投稿の通知をメールで受け取るには、メールアドレスを入力してください。