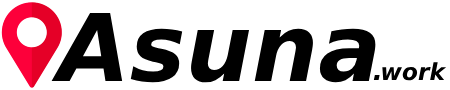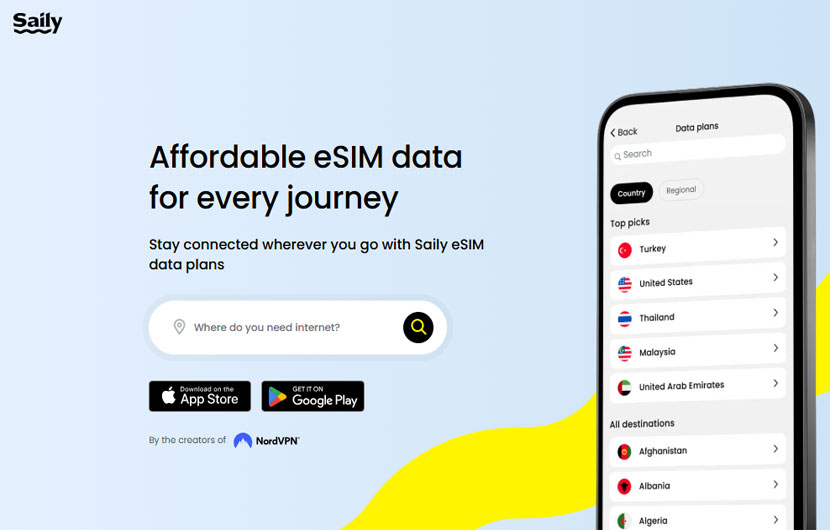ロンリープラネットからの素晴らしい読み物: TC ボイル著「緑の輝きの国」
旅行制限やロックダウンが続く中、私たちは素晴らしい旅行記のカタログを探索し、大小さまざまな旅の物語を深く掘り下げています。
TCボイルのこの作品は、アイルランドでの海外生活について語っています。ロンリープラネット旅行アンソロジー。

私の母方の祖母はマクドナルドで、フィッツジェラルドと結婚しました(ただし、ポストという名の謎めいたオランダ人が表面上は私の母の父でした)。そして私の父方の祖父はボイルでした。そこで何が見つかるか怖くて家系をたどったことはありませんが、私は少なくとも半分はアイルランド系だと考えています。これはある種の民族的アイデンティティを主張するのに十分なことです。そこで、40歳の春、妻と3人の幼い子供たちを連れて、3か月半の間アイルランドに移住しました。先祖の土地で暮らすとはどういうことかを知るためでした。シャムロック島に降り立ったほとんどのアイルランド系アメリカ人(マーフィー!このパブにマーフィーはいますか?)とは異なり、私には家族のつながりも、特に目的地もありませんでした。 私はアイルランド観光局の援助を得て、スキバリーン郊外のロー・ハイン湖にある 18 世紀の豪邸を借りることになり、短期間、(代用の)領主の役割を担うことになりました。
「ああ」彼らは「作家だ」と言い、それですべてがわかるかのように私のパスポートに力強くスタンプを押した。
早朝の薄暗い霧の中、アフリカの奥地まで探検旅行に行けるほどの荷物(ベビーシート、ベビーキャリア、ベビーオムツ、その他の幼児用装備が大部分を占める)を抱えてシャノン空港に到着した私は、アイルランド人との最初の出会いが、控えめに言っても縁起の悪いものだったことに気付いた。入国管理局の職員は、私たちを難民として送り返そうとしていた。私たちは偽りの口実で入国し、明らかに国の保護下に置かれ、おまけに乞食になるに違いない。私は妻に交渉を任せた。妻はほっそりとしていて、愛想がよく、温厚で、何よりも分別がある。私はその場所と時間に、絶対に分別がなかった。赤ん坊は悲鳴をあげ、荷物は山積みになった。税関職員は疑わしげな顔をした。ついに私は、いらだちながら自分の用件を説明した。「私は作家です」と。彼らは、喜びとまでは言わないまでも、理解して顔を輝かせた。 「ああ」と彼らは言った。「作家だ」と、まるでそれですべてが説明されるかのように、私と妻と子供たちのパスポートに力強くスタンプを押した。その中には、パスポート写真にとても大きな手(私の手)で支えられている写真が載っている一番小さな赤ちゃんも含まれていた。
ロサンゼルスからの一日中、一晩中続く旅の疲れ果てた後に続いたのは、Google がまだ登場していなかった、縮小されたアイルランドの道路を次々と下って、借りた家までの道を探し求めることだった。しかも、そのすべてを道路の反対側(つまり間違った側)を運転しながら。
ようやく到着すると、不在地主に代わって家と農場の維持管理を担当していた地元の農家、メアリーとパディ・バーク夫妻が案内してくれた。家は、私たちが住んでいた、干からびて太陽が照りつけるロサンゼルスの家の 6 倍の大きさで、大きな玄関ホール、さまざまな応接室、図書館があちこちに点在し、謎めいた棟が次々と続いていた。メアリー・バークは、私を案内しながら、ユーティリティやリネン クローゼットなどの詳細を聞き出そうとしていたに違いない。すでに私たちの上の寝室では、赤ちゃんがわんわんと泣きながら眠りについていた。窓の外には、ローフ・ハイン湖に面した広大な起伏のある芝生があり、おそらく 12 頭ほどの牛がいた。私はメアリーに、彼女をだましてこう言った。「実は、私は家畜にあまり詳しくないんです。雨が降ったら、牛が濡れないように家の中に入れないといけないんですよね?」メアリーは笑い出し、私たちはすぐに友達になった。 彼女はアイルランド人であり、私もそうでした。
次に重要なことは、生き延びることではないにしても、娘の学校教育でした。ケリーは当時2年生で、学期があと7週間残っていたとき、私たちはロサンゼルス学区の束縛から彼女を解き放ち、無礼にも緑の輝きの国へと連れ去りました。

そこで、到着した翌日、私はボルチモア(バール・ティー・マール)のラス・スクールの校長マイケル・コリンズに電話をかけ、私たちの状況を説明した。私たちは納税者でも市民でもないが、娘は学校に通う必要があり、彼は私たちを助けてくれるだろうか?「彼女を連れて来なさい」と彼は言った。翌日、彼の指示に従って、私はレンタカーで、真ん中に膝の高さの草が生えている舗装されていない道を15分ほど走った。羊と緑の丘、そして時折見える農家以外には道しるべは何もなかったが、語られた奇跡やがて、ラス スクールが、海の波と裂け目から灯台のように浮かぶ、長く深い緑の丘のふもとに現れました。マイケル自身が私たちに挨拶してくれました。「半日待って、彼女が順応するかどうか見てみましょう」と彼は言いました。私が彼女を迎えに戻ると、校庭の全員が車に駆け寄って手を振って別れを告げ、子供たちの声が合唱して「さようなら、ケディ、さようなら!」と叫びました。
私にとって初めての海外生活でしたが、とても満足し、魅了されました。
ここで私が言おうとしていることは何か。私が経験したアイルランドは、スモッグで覆われ高速道路が渋滞するロサンゼルスとは正反対の、リラックスした歓迎的な場所だったということ、バーク一家は素晴らしい人々で、マイケルは私の親友の一人になったということ、そして今でもそうだということ。そして、私たちは村に住んでいて、子供が地元住民の子供たちと一緒に学校に通っていたため、平均的な観光客(マーフィー?ここにマーフィーはいますか?)が経験するであろうものとは大きく異なる生活様式に陥ったということ。これは私にとって初めての海外生活であり、私は深い満足感を覚え、魅了されさえした。ロサンゼルスは瞬時に全く別の世界へと追いやられた。
牛がいた。湖に続くシャクナゲの庭があり、手漕ぎボートがあり、畑があり、長く曲がりくねった砂利道があり、牛が畑や庭に入らないようにするための一連の古い鉄の門があった。そして郵便配達員がいた。当時、私は膨大な小説の校正に取り掛かり、さまざまな雑誌に小説を送っていたため、郵便配達員の存在と仕事は私にとって不可欠だった。毎朝、長い道のふもとにある牛の門を開けると、彼は静かに通り抜け、止まって門を閉め、車に戻って丘を上って家まで行き、大きな玄関ホールに静かに入ってきて、そこにあるテーブルに手紙を置いた。何よりも良かったのは、雨が降っていたこと、雨がずっと降っていたこと。これは、夏の焼けつくような暑さの中で、LA の太陽の乱舞と果てしない日々を戦わなければならない作家にとって、決して小さくない慰めだった。
勇気を出して、最も素朴な雰囲気のパブに行ってみました...
もしこれが執筆に適した天気だったら(そして私はロー・ハイン湖で過ごした間、私の3番目のコレクションを構成するほとんどの物語を執筆して生産的だった)、もし川がウィスキーだったら)、お酒を飲める気候でもありました。その時代、スキバリーンは人口約 3,000 人の町で、およそ 70 軒ほどのパブがありました。私はそれらのすべてを訪ねたとは言えませんし、半分も行ったとは言えません (まあ、3 分の 1 くらいは行ったかもしれません)。もちろん、ボルチモアやスカルにも、タイミングよく立ち寄る価値のあるパブが 1 軒か 2 軒ありましたが、本当に満足できるパブをすぐに見つけました。最初は、外国人で、どのような対応をされるのかよくわからなかったので、入るのにためらいがありましたが、すぐにその気持ちは克服しました。数日そこに滞在した後、勇気を出して、とても素朴な外観のパブに行ってみました。そのパブは、ピカピカに光り、きちんと積み重ねられたアルミの樽が 50 個ほど飾られた石造りの路地の奥にありました。 妻も一緒にいたので、当時のバーが男女別だったかどうかわからなかったので(あるバーでは、女性を伴わない男性は別の部屋に閉じ込められていた。これは、おそらく歴史上の血なまぐさい出来事が原因だろう)、ためらいながらドアを開けて中を覗いた。そこは細長い場所で、10 脚か 12 脚のバースツールがぎっしりと並んでいた。それぞれの椅子には、ツイードのジャケットとツイードの帽子をかぶり、実用上(雨、泥、汚物)に履いている黒い長靴を履いた農夫が座っていた。彼らは皆、鋭い目と野蛮な嘴を持つサミュエル・ベケットの双子だった。全員が一斉に顔を向け、私はウラジミールとエストラゴンのことを考えながら、静かにドアから退出し、後ろでドアを閉めた。
一週間後、もっと慣れてきて、銀行の店員や八百屋、肉屋三軒とも知り合いになった私は、そのパブに戻り、ベレー帽をかぶって、カウンターの上の薄暗い鏡に映る、かすかにベケット風の自分を眺めながら、楽しく騒いだ。半インチのクリーミーな泡が表面に浮かび、完璧な黒さになるまで、ギネスビールを待っていたことや、必然的にジョン・パワーズ・ウイスキーの小さなグラスが添えられていたことを覚えている。そして音楽。音楽は絶えず流れていて、クリア島の学校のパレードや地域のお祭りが中止になった大雨の日には、私たちはそこにある三軒のパブに押し寄せ、誰もが、奇妙な口琴、バンジョー、カチャカチャと鳴るスプーンの伴奏で、自然に歌い出した。 何よりも私が覚えているのは、湿った野原と霧のかかった湖、そして大きな古い家に静寂が訪れたこと、そして私たち5人が泥炭の火を囲んで物語を読んだこと、時間よりも長い時間の中で、すべてがうまくいっていたこと、大丈夫だったこと。
この旅行は人生を変えるものでしたか? いいえ...ただ人生を生きることでした。
この旅は人生を変えるものだったか?いいえ、フランナリー・オコナーやジョン・コルトレーンを発見したという意味ではありません。ただ人生を生きることだったのです。その夏、私はジョイスの『ダブリン市民』『肖像』『ユリシーズ』を読み直し、シングの『愛の詩』の公演にも行きました。西洋のプレイボーイシャーキン島の小さな石造りのコミュニティ ビルで、初めて本当に、実際にそれが何なのかを理解しました。それは人生を変える出来事でしたか? おそらくそうでしょう。しかし、すべての経験、すべての瞬間はそうなのです。何年も経った今、カリフォルニアのセントラル コーストの荒れ狂う海を見つめながらも、シナプスの中にアイルランドを見ている今この瞬間もそうです。重要なのは、それ以来何度も島に戻ってきましたが、それはいつも仕事のため、つまり本のビジネスのためだったということです。一方、あの輝かしい 3 か月半の間、私は住み、書き、異国でありながら親しみのある場所に真に住むことができました。そして、それがすべてを決定づけました。
あなたはおそらくそれも好きでしょう
家から出ずに言語を学ぶ方法
神話を現実に変える:ティンババティの白いライオン
アイルランドでゲール語を学ぶことで語彙が増えただけでなく、
サブスクリプション
サイトの新着記事を購読し、新着投稿の通知をメールで受け取るには、メールアドレスを入力してください。